将来は山暮らしして自分達の食べるものはできる限り自給したいと思っている@Kamigurashiです。
↓山暮らしの土地ゲットしました!
基本的な野菜はもちろん雑穀に至るまで多種多様な品目を育てたいと思っています。
できる限り持続可能な方法でやりたいので、我が家では自然農や自然菜園などの方法を取り入れて挑戦しています。
現在はまだ山暮らしではありませんので自宅の庭を菜園にしたり、父の実家の畑などで実験を兼ねて色々試しています。
この記事では以下のような事について書いています。
- 自然農・自然菜園でのジャガイモ栽培の基本的な情報
- 我が家の栽培記録を通したジャガイモ栽培の実際
ジャガイモの栽培【基本情報】
まずは自然農や自然菜園でのジャガイモ栽培の基本的な情報から。
| 原産地 | 南米アンデス高地 |
| 土ステージと適地 | ステージ1〜2/pH5.0〜6.0の酸性、やせて乾燥土壌 |
| 適期 | 春植えと秋植え |
| コンパニオンプランツ | ジャガイモ↔ネギのセットで毎年同一畝の交互連作 |
| 種いも | 長期保存向きは「メークイン」や「ダンシャクイモ」などの休眠の深い品種を。長期保存不向きでは「キタアカリ」「アンデスレッド」「農林1号」「ハナシベツ」「グラウンドペチカ」などがある |
種イモの準備
ウイルス感染のない専用の種イモを購入して植える。自然農で無肥料栽培したイモは翌年の種イモにできる。60g〜80gのSサイズイモが最適。
病気に強くするため1週間ほど日光にあてて緑化させる。また、イモの頂部から出る芽は取ってしまいます。
自然菜園の竹内さんは、頂部の芽をイモごと削り取る格好で取ることを勧めてらっしゃいます。
また、ガッテン農法の三浦さんは頂部の芽を取るのは竹内さんと同じですが、逆側のへそのある方を削り取ることを勧めてらっしゃいます。

このあたりはどちらが正しいとかでは無く、育てる環境やイモの種類によっても違うでしょうから色々試してみて最適な「我が家手法」を見つけるのが良いかと思います。

我が家もまだまだ色々実験中ですよ〜
植え付け
ジャガイモは遅霜で枯れてしまうリスクがあるため、必ずサクラの花が咲いてから植える。また、28℃以上でも枯れるため遅くなりすぎるのもNG。
浅めの溝(深さ10〜15cm)を掘り種イモを置く。この時ガッテン農法の三浦さんによれば猫じゃらしやメヒシバの枯れ草を敷き少し土をかけて、その上にイモを置くと微生物が活性化し地温が温まりやすくなるので良いそう。
イモの向きに関しては諸説あり、これまた色々試して最適な手法を見つけるのが良さそう。
コンパニオンプランツ
ジャガイモはネギがコンパニオンプランツとして相性が良い。また、ネギと交互連作することで毎年同じ畝で連作できる。
ジャガイモをはじめとするナスやピーマン類などのナス科は連作障害が起きやすいですが、ネギと交互連作することでジャガイモの畝を毎年変更しなくても良いため、他の野菜の計画が立てやすくなります。
株間
ジャガイモを植える場合の株間は約30cmほどが良いようです。
条間は50cmほど取る。
土寄せ・草マルチ
植え付けて1ヵ月ほどで芽が出る。週1くらいのペースで葉のすぐ下まで土寄せする。ジャガイモは茎が土中で根に変化したものなので、茎が露出しているとイモがつかなくなります。

我が家の2019年は完全に茎が露出していたので、そりゃああまりイモが出来ない訳です。(後述の記録参照)
6月頃に蕾がついたら根の生育は止まる。株元を草マルチで覆い始める。地温の上がりすぎはNGなので草マルチを重ねてできる限り地温が上がらないようにする。
収穫
ジャガイモの収穫時期は春植えで6月下旬〜8月中旬。秋植えで11月上旬頃となります。新じゃがは食べる分をその日に収穫。保存用は葉や茎が完全に枯れてから収穫する。
ジャガイモの栽培:参考資料
ジャガイモの栽培記録
ここからは、実際にジャガイモ栽培をした記録です。
2022年からは岡山で本格的に菜園を開始した記録となります。
2021年までは自宅菜園での記録です。造成地を住宅地にしたためあまり土の状態は良くありません。コンクリートの塀に囲まれているからか、ダンゴムシも多くアリも多いです。
ジャガイモの栽培【2023年】
2023年のジャガイモ栽培の記録です。昨年から岡山でのジャガイモ栽培に移りました。
昨年の畝は1.2m×7mのサイズでしたが、本年より1.2m×4mを2畝という体制です。

同じサイズの畝を使うことで、春秋のローテーションのしやすさを狙いました。
昨年は50年以上も放置されていた水田跡の山林を開拓したばかりでのジャガイモ栽培ですので、笹などの落ち葉堆積がスゴくて富栄養化状態でのスタート。
数年間は失敗してもひたすら栽培を続けて余分な栄養素を抜いていかないといけません。
春作
浴光させ芽出しをしていた種いもを、植え付けの3日ほど前に種いものへそ側(ストロンのあるほう)を切り欠きました。


へそ側を切り欠くことで発芽が促進されます。
このまますぐ植えてしまうと水分が多く痛む恐れがあるので、植え付け当日まで乾燥させます。
植え付け前日です。乾燥して切り口がシワシワになりました。


こうなれば植え付け準備完了です!
昨年は、桜の開花を待って植え付けをしましたが、収穫のタイミングを逃してしまい秋作のスタートが遅くなってしまいました。
本年は、試験的に桜の開花を待たずに植え付けしてみることにして、セオリーに反して昨年より約3週間ほど早めの植え付けです。

本年も植え付けする品種はデジマとアンデスレッドです。
昨年の春作・秋作を経てつないだ種芋で植え付けできるのは感動すら覚えます。

自給の第一歩を踏み出せました。これからずっとつないで行きたいですね。
寒い日が結構続き、なかなか地中から芽を出してくれませんでしたが4月9日にデジマ、アンデスレッドともに発芽を確認できました。


約1週間後です。アンデスレッド、デジマともに順調に成長をはじめています。


4月22日、アンデスレッド・デジマともに元気です。芽かきと土寄せをしておきました。



2023年の芽かきは2本に仕立ててみました。
5月16日にはアンデスレッドの花芽を確認しました。

6月20日です。葉が枯れはじめているのを確認しました。そろそろ収穫時期ですね。

雨が続いてなかなか収穫できなかったのですが、7月7日雨の合間を縫って収穫しました。

本当は晴れ間が2〜3日続くときに収穫したいのですが、まだ住んでいるわけではないのでなかなかタイミングが難しいです。


年を追うごとにいもが立派になってきているのを実感します!

つづきはまた更新します。
ジャガイモの栽培【2022年】
2022年春のジャガイモ栽培の記録です。今年から岡山で本格的に自給できる体勢を目指していきます。
50年以上手付かずで竹林に覆われた土地を開墾して畑にしています。つまり初年度の挑戦ということになります。
これまでは1m×2mの面積で栽培していましたが、今年は1.2m×7mの面積にグレードアップ!
種芋の数も必要個数がめっちゃ多くなります。
今年は「デジマ」と「アンデスレッド」の2品種を栽培することになりました。
うまくいけば今後、収穫したイモから種芋を選出し春作から秋作、そして毎年つないでいけたらと思います。
初年の主な条件は以下です
- 開拓したばかりの畑のため草が生えていません
- 水田跡地の為水捌けがあまりよくありません。
- 50年放置され、枯れ葉や枝が堆積し富栄養化していると思われます。
春作
事前準備として種芋のへそ部分のカットと芽かきをして乾燥を行ってあります。


芽出ししていた種芋のへそ部分を切ります。


今年は逆さ植えに挑戦するので、逆さにした時に真下に来る芽も欠きました。



これは意味がなかったかも知れません(汗)
畝幅120cmの畝の両端に株間30cmで植え付けしました。中央にはネギが来る予定。

4月16日には、無事にデジマの発芽を確認しました。

右列のアンデスレッドもデジマほどではありませんが、ちらほら発芽を確認できました。

ゴールデンウィークには随分成長しているのを確認。茎の伸びるスピードが早すぎるのが気がかり・・。なんだか間延びしてます。

株元はこんな感じになって来たので、土寄せと芽かきをします。


5月22日にはアンデスレッドの開花を確認しました。

ここで、カメムシがついているのを発見しました。写真がピンボケで申し訳ありませんが、中央の赤丸部分にカメムシの姿が発見できると思います。


ジャガイモにカメムシが着くのを初めて見ました・・・
おそらく、長年の有機物(枯れ葉など)の堆積があったため一部の栄養素が突出して存在しているからだと思います。
少し日数が飛びますが、7月に確認するとほとんど倒伏してしまいました。

これまでの成長を見ていると、全体的に茎が間延びしているな・・・と思っていました。
やたら背の高いジャガイモになっていたため、強い風が吹けば倒伏するのは当たり前ですよね。
倒伏してしまってから、翌週ですが収穫してしまいました。



40個植えたにしては少し少ないですが、初年度にしては上出来ではないでしょうか!
このジャガイモから秋用の種芋をより分け、残りをおいしくいただこうと思います。
秋作
9月に入ったので、さっそく浴光させ芽出ししていた種芋を植えました。

春作は両サイドに植えておりましたが、今回はネギの植っていた真ん中にデジマとアンデスレッドを交互に植え付け。

春の植え付けの時より少し土の状態が良くなっています。
植え付けから2週間後、発芽して順調な成長を確認。

少し開いて10月20日に確認すると、やはり春作同様間延びして育っています。

途中、やはり倒伏しており今回は花も咲きませんでした。
そのまま秋作ジャガイモを収穫しました。

また、この採れたジャガイモから種芋をより分けたいと思います。
2022年以前の栽培記録は次ページへ。
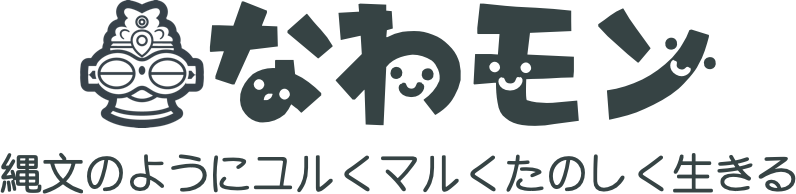








コメント