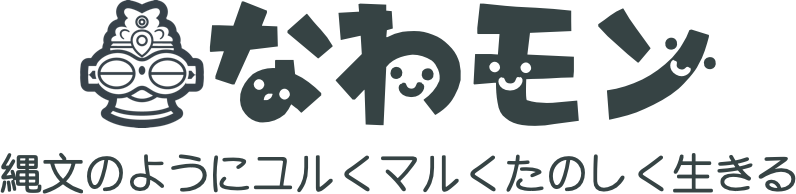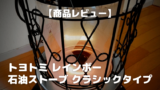山暮らしのライフラインについてまとめます。
基本的には社会情勢に左右されにくいオフグリッドを目指して構築していきます。
ここで取り扱うライフラインは主に以下の7点です。
- 水
- 火
- 電気
- 通信
- 生活排水の浄化システム
- トイレ
- 風呂
このうち、通信だけはオフグリッドで構築するのは難しいです。ただしインターネットに接続しないのであれば可能です。
我が家のスタンスはインターネットじゃなくても可能なもの(スケジュール管理・クラウド利用をやめる)は徐々にアナログ化しています。
水
開拓当初は敷地内を流れる川から竹筒で水を引き、洗い場を作りました。飲料水はペットボトルの飲料水を購入して持参していました。

洗い場を作ったら簡単な水質検査もしました。
現在は、洗い場はそのままに、飲料水は石垣から湧き出る水をソーヤーフィルターを通してろ過して利用しています。

最近、宅水検の「飲料水安心コース」という水質検査で検査をお願いして、飲用可の報告をいただきましたのでそのままでも飲めることがわかり喜んでいます。
火
開拓当初はそのへんの石で囲い、簡単なかまどを作って調理や暖をとっていました。

初年度(2021年)の年末(開拓から約半年)、ベルテント導入とともに薪ストーブが始動しました。
これで夏場は焚き火場、冬場は薪ストーブも併用することになりました。
そして3年度目(2023年)の5月頃、かねてより作りたかったロケットストーブを作成しました。

ロケットストーブは熱効率が良いので、小さな枝などでも十分な火力を得ることができてより効率的に。
2025年現在は、さらに改良した1斗缶ロケットストーブを使っています。

改良型は一番損傷する焚口を頑丈な耐火煉瓦で作り煙道兼炎の通り道部分は1斗缶で作っています。

これにより、敷地内で無尽蔵にあふれている竹を薪として使えるようになったのが大きいです。
これまで開拓当初からカセットコンロは常にサブとして併用しておりましたが、少ないとはいえ空の缶が増殖していくのはなんだか無駄が多い気がして、3年度(2023年)の冬には、灯油コンロも導入しました。
火力も強く、使う灯油の量も少ないのでとても重宝しています。電気を使わず、マッチで点火できる点も気に入っております。
灯油を使うものとしては現在(移住前の自宅)で使用している、電気を使わない石油ストーブも引き続き持ってくる予定。
電気

2025年現在は200Wの多結晶パネル3枚で発電し、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V100Ah×4台(1280w×4=5120w)に蓄電しています。

当初はディープサイクルバッテリー12V100Ah×2(1280w×2=2560w)に蓄電、さらにそこから500wのモバイルバッテリーにも充電蓄電し使用していました。
しかし未だテント暮らしの為、2025年初頭の寒波で氷点下に耐えられずBALDRのポータブルバッテリーがお亡くなりになりました。
ディープサイクルバッテリーは比較的寒さに強いですが、リチウムイオンは低温に弱いという性質でモロに被害を受けたため、新しいシステムでは寒冷地向きの低温保護機能付きにしました。
かなりの出費(約30万円)になりましたが、上手に使えば50年は使えるし今後電気代が発生しなくなるので思い切って購入しました。
山でミニマムに暮らすため、家電依存(テレビ・洗濯機・電子レンジ・炊飯器など)を減らしてきましたが洗濯機(2層式)だけは今後導入したいのでバッテリーの増量に踏み切りました。
我が家は冷蔵庫やエアコンも手放す予定なのでこのバッテリー容量ですが、冷蔵庫やエアコンを使用したい場合はこのシステムでは心もとないと思いますのでご注意ください。

冷蔵庫・エアコンは最も電気を消費する家電のひとつです。
通信
山の中というのもありますが、通信機器を置きたい場所は谷ですので、さらに通信会社の電波は届きにくいです。
電力会社から電気を引かないというのもあり、光回線は望めないので電波を直接キャッチするルーターを使う必要があります。
格安SIMを色々試してみて、当地はソフトバンク系を良く掴むことがわかったので、格安SIMを挿せるLTEホームルーターをテントに設置しました。
ちなみに使用しているSIMカードはマイネオのマイそくプレミアム(最大5Mbps)です。
月額2200円で3日間で10GBを超えなければ使い放題のプランです。ただ欠点があり、平日のお昼12時代は200kbpsと低速になります。

時間を気にする生活をしていないので我が家には全く問題なし。YouTubeもやたら高画質にしなければ快適に観れます
生活排水浄化システム
オフグリッドで生活するうえで問題になるのは、生活するうえで必ず出る排水をどうするかという問題です。
排水には主に2種類あって、英語でいうところのブラックウォーターとグレイウォーターです。
- ブラックウォーター:下水(主にトイレからの排水)
- グレイウォーター:生活排水(主に風呂、洗面所、台所からの排水)
一番問題のブラックウォーターはコンポストトイレなのでそもそも排水が出ませんので、グレイウォーターの風呂、洗面、台所からの排水の処理方法を考える必要があります。
排水の処理方法で最適な方法は「バイオジオフィルター」システムを採用することです。
下の写真は我が家の制作中のバイオジオフィルターです。幅30㎝深さも30㎝くらいの溝を掘り、底に段ボールなどを敷いたあと防水シートを被せます。

1mおきに堰を作り、オーバーフローした水が次の区画へ移動するように作ります。
入れる「ろ材」は軽石や炭、土でできた瓦を細かく割って入れることもできます。バクテリアの働きで浄化するため、とにかく多孔質の材を使用することが重要です。
我が家は底には軽石、上には毎日ロケットストーブから出る竹炭を入れています。(製作中)

だいたい10mくらいあればきれいに浄化できるようです。バイオジオフィルターでは空心菜やマコモなどを育てることができます。
空心菜は栄養が高い水を好むのでよく育ちます。最後のほうの区画ではワサビも育つくらい水が浄化されるそうですよ。
さらに台所からの排水は非常に脂分や栄養が多いため、バイオジオフィルターをできる限り汚さないように、一旦「傾斜土層法」と呼ばれる装置を経由するようにします。
我が家は軽石を詰めて、シマミミズさんに浄化を手伝ってもらう予定です。
自分で一から作るのもよいですが、花水土(はなみづち)という製品を利用するのも手です。
花水土(はなみづち)は三共機械工業さんで購入できます。
10mのバイオジオフィルターで浄化された水は最後にビオトープへと流れ込みます。すでにバイオジオフィルターできれいにはなっていますが、ビオトープで時間を掛けてさらなる浄化を促します。

トイレ
開拓当初は、敷地内の適当な場所に穴を掘って排泄していました。掘った穴が埋まって来たら土を埋めなおして新たに違う場所に穴を掘って移動していました。

その後、2代目はペーパーホルダーなども設置しグレードアップ!


トイレットペーパーは、土に埋めてしまうと分解に時間がかかるので燃やしてしまったほうがいいです。
そして現在は、コンポストトイレも作成しトイレ小屋(作成中)に設置して使用しています。

トイレ小屋は現在も継続作成中です。外装は8割方できていて、今内装を作成しはじめたところです。

屋外で超寒いので、使わないマットレスを切って断熱材代わりに詰めています。

照明は、トイレだけで完結するようにメインの発電システムとは別に構築しています。

バッテリーは某カー用品店で車のバッテリーを新調したときに出た廃棄バッテリーをそのまま持って帰って使っています。
車のバッテリーとして使うにはダメですが、LED電球を灯す程度の電力ならばまだまだ使えます。
発電のパネルとチャージコントローラーは通販で調達しました。以下はバッテリー付きですが、バッテリーなしもあります。
風呂
執筆準備中